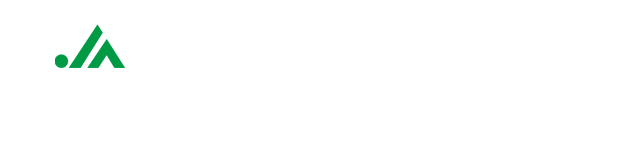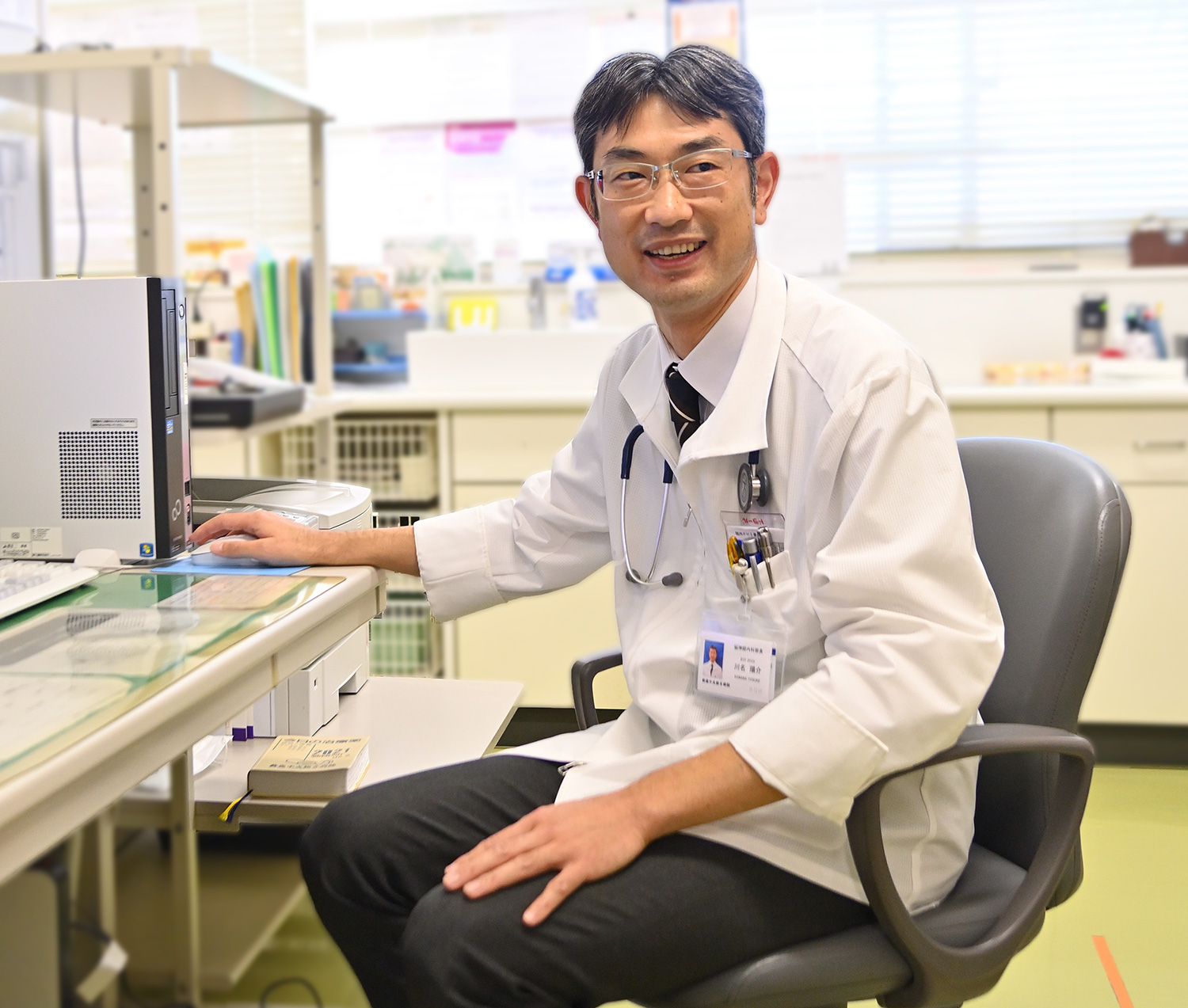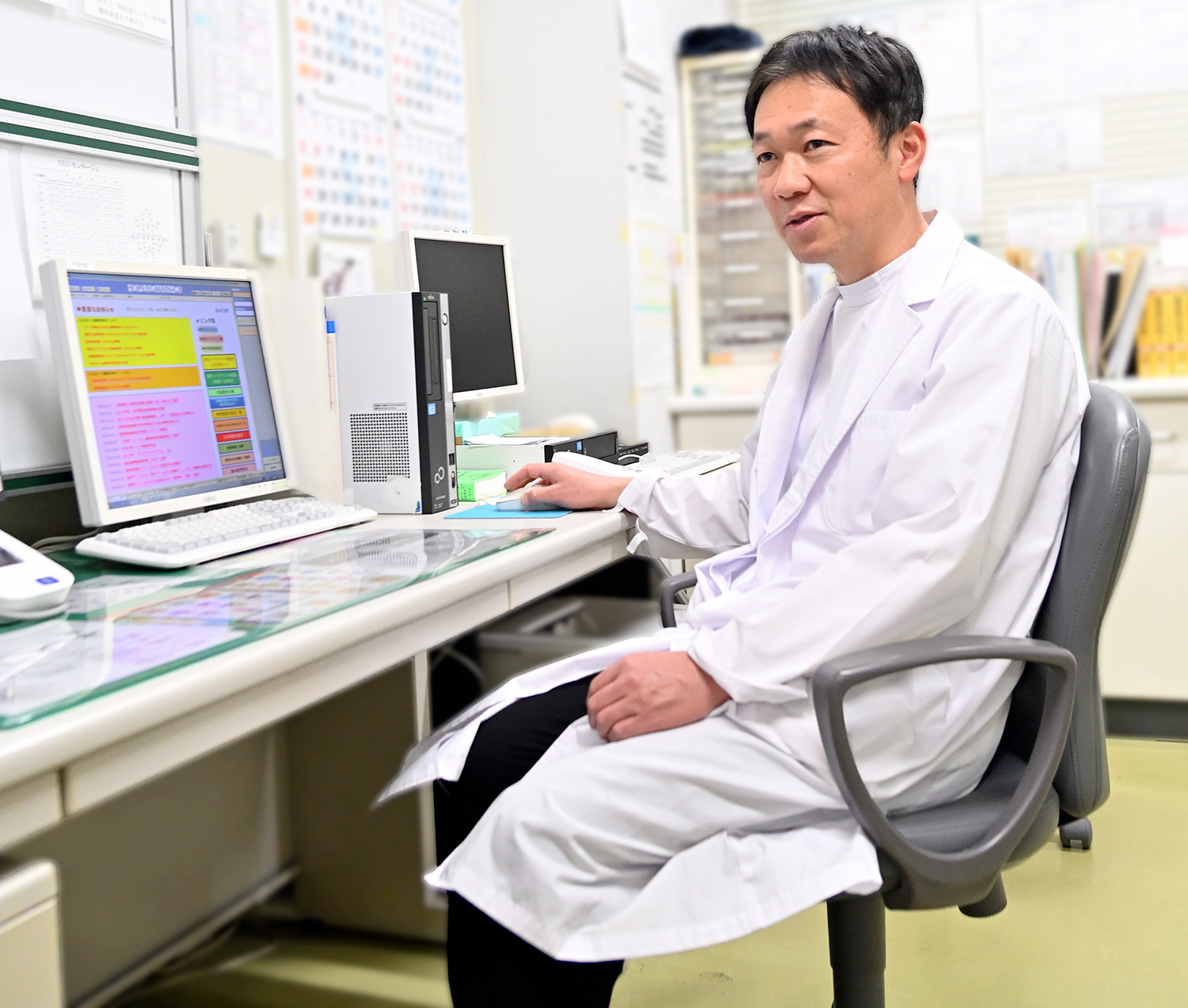外来担当医表
| 診療科 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
特徴
脳や脊髄、神経、筋肉の病気を診る科です。体を動かしたり、感じたりする事や、考えたり覚えたりすることが上手にできなくなったときに脳神経内科の病気を疑います。症状としてはしびれやめまい、うまく力がはいらない、歩きにくい、ふらつく、つっぱる、ひきつけ、むせ、しゃべりにくい、ものが二重にみえる、頭痛、かってに手足や体が動いてしまう、ものわすれ、意識障害などたくさんあります。このような症状を起こす病気としては、脳血管障害(脳梗塞、脳出血など)、神経変性疾患(パーキンソン病、筋萎縮性側索硬化症など)、神経感染症(髄膜炎、脳炎など)、末梢神経障害(糖尿病性神経障害、ギランバレー症候群など)、筋疾患(重症筋無力症、筋炎、筋ジストロフィーなど)、頭痛性疾患(片頭痛など)、てんかん、認知症性疾患(アルツハイマー病、レビー小体型認知症、正常圧水頭症など)など多岐にわたります。
当科は地域中核病院の脳神経系疾患の治療の一端を担っており、脳血管障害の急性期の対応や、意識障害や痙攣などの神経救急疾患の対応が24時間できるように診療体制をとっています。このような急性期治療だけでなく、神経変性疾患など治療が長期にわたる疾患の診療も、入院・外来で行っています。
当院は、日本脳神経学会の教育施設、日本脳卒中学会の一次脳卒中センターに認定されています。
代表的な疾患・治療
対応疾患
脳梗塞、パーキンソン病、てんかん、アルツハイマー病
疾患別案内
何らかの原因で脳を栄養する血管がつまってしまい、血液が流れなくなることによって 酸素不足・栄養不足におちいった脳の神経細胞が死んでしまう病気です。
| 原因 | 動脈硬化により細い血管が閉塞したことによるラクナ梗塞、太い血管が閉塞したことによるアテローム血栓性脳梗塞、不整脈のため心臓の中にできた血栓が脳へ飛んできて血管がつまることによる心原性脳塞栓の3種類に大別されます。 |
|---|---|
| 症状 | 体の片側だけが動かなくなる片麻痺、ろれつが回らない、言葉が出てこないといった言語障害や意識障害などが主な症状です。これらは突然起こりますが、一時的に症状が消失する場合もあります。 |
| 検査・診断 | 頭部MRIやCTを用いて部位や範囲を確認します。また、原因を特定するために心臓超音波検査や頸動脈超音波検査、心電図検査なども行います。血管の状態によっては脳血流シンチ、血管造影検査を行うことがあります。 |
| 治療 | 発症早期に受診した場合には、t-PAの点滴による血栓溶解療法やカテーテルを用いた血栓回収療法の適応があることがあり、後遺症の軽減が期待されます。 これらの治療適応がない場合でも、抗血小板薬や抗凝固薬、脳保護薬の点滴やリハビリテーションを行います。再発予防のため、食事・禁煙・運動などの日常生活管理も重要です。 |
脳の神経細胞に異常が起こることで、体を自由に動かせなくなるなどの症状が次第に進んでいく病気です。
| 原因 | 脳の幹にあたる黒質という部分の神経細胞が次第に減少し、その神経が働くときに使うドパミンという物質が減ることによって起こります。 |
|---|---|
| 症状 | ドパミンが減少し、運動の調節機能が損なわれるために体の動きが不自由になります。典型的な症状としては動きが鈍くなる(無動)、筋肉がこわばる(筋強剛)、安静時の手のふるえ(振戦)、転びやすくなる(姿勢反射障害)などがあります。 |
| 検査・診断 | 臨床症状から判断し、MIBG心筋シンチグラフィー(心臓の交感神経機能を見る検査)やDAT スキャン(頭の中のドパミンの放出量を見る検査)といった検査を行うことで診断の裏付け行うことが可能です。 |
| 治療 | 不足してしまったドパミンを補う薬を投与することで症状の緩和を図ります。リハビリテーションも並行して行います。病状によっては脳深部刺激療法(DBS)やレボドパカルビドパ経腸療法 (LCIG) といったデバイス補助療法と呼ばれる治療法の適応が考慮されます。 |
脳の神経細胞の過剰な電気的興奮に伴って、意識障害やけいれんなどを発作的に起こす慢性的な脳の病気です。
| 原因 | 脳の一部の形態の異常、脳外傷、脳炎、脳症、髄膜炎、脳梗塞など様々です。しかし原因がわからないもの(特発性)も多くあります。 |
|---|---|
| 症状 | 全身のひきつけで起こるもの、部分的にひきつけが出るもの、意識を失うもの、行動はしていても後で気づいたときに記憶がないもの、口をもぐもぐさせるもの(自動症)などがあります。 |
| 検査・診断 | 問診(病歴聴取)が非常に大切で、脳波検査も診断の決め手になります。 てんかんの原因を調べるために、頭部MRIなどの画像検査を行うことがあります。 |
| 治療 | 抗てんかん薬を毎日規則的に服用し、発作を抑制していく薬物療法が主流です。 その他にも外科治療などもありますが、まずは十分な薬物治療を行って、期待した効果が得られないときに検討をします。 |
もの忘れを主な症状として、認知症がゆっくり進行する病気です。
| 原因 | 脳内にアミロイドβと呼ばれるタンパク質がたまり、神経細胞が壊れて死んでしまうためと考えられています。 |
|---|---|
| 症状 | 初期症状として多いのは物忘れです。同じことを何度も聞く、物を置いた場所を思い出せない、日付や季節が分からない、などの症状が起こります。中期症状としては、自宅などなじみのある場所が分からなくなり、「ものを盗まれた」という妄想や、夜中に徘徊するといったことがみられるようになります。うつ状態や興奮、いらいら、暴力などの症状も出てきます。さらに進行すると、言葉が分からなくなって会話が難しくなり、身体能力も奪われていきます。 |
| 検査・診断 | 主に病歴などの問診、認知症かどうか調べる簡単なテストなどを行った後、血液検査や頭部MRI、脳血流シンチなどの検査をします。MRIによる脳の萎縮パターンや、脳血流シンチによる血流低下パターンを確認し、他の認知症の可能性を除外することにより、アルツハイマー病の診断を行います。 最近ではアミロイドPET検査を行うことがあります。これはアルツハイマー病の原因と考えられる脳内のアミロイドβ蓄積の有無や程度を調べる検査になります。かなり早い時期に異常を検出する事ができますが、高額の検査で、保険適応になる条件も限られます。 |
| 治療 | もの忘れに対してはコリンエステラーゼ阻害薬(リバスチグミン、ガランタミン、ドネペジル)やNMDA受容体拮抗薬(メマンチン)が用いられ、残っている神経細胞の伝わりをよくするなどして症状の緩和を図ります。これらは根本的に治す治療法ではありませんが、記憶障害の進行を遅らせることができる可能性があります。 新たな選択肢として大きな期待を集めているのがレカネマブとドナネマブという2つの薬です。これらは原因物質とされるアミロイドβを除去し、症状の進行を遅らせる効果があり、アルツハイマー病による軽度認知障害(MCIと呼ばれる状態)や、軽度認知症の方を対象にその効果が期待されます。 うつ状態には抗うつ薬なども使用され、幻覚・妄想には漢方薬の抑肝散や、向精神薬を使用します。薬による治療の効果は現時点では限定的であるため、家族と医療・介護従事者による周囲のサポート体制が重要になります。 |
医師紹介
地域の神経疾患の医療に貢献できるよう努めます。 |
|
経歴
三重大学 脳神経内科一般 専門医など日本内科学会 総合内科専門医 |
よい医療を提供できるよう努めます。 |
|
経歴
三重大学 脳神経内科一般 専門医など日本内科学会 総合内科専門医 |
地域の神経疾患の医療に貢献できるよう努めます。 |
|
経歴
三重大学 脳神経内科一般 専門医など日本内科学会 内科専門医 |
至らぬ点も多々あると思いますが、日々精進して参りますのでよろしくお願いいたします |
|
経歴
三重大学 脳神経内科一般 専門医など
|
鈴鹿市の医療に貢献できるよう日々精進致します。 |
|
経歴
愛媛大学 脳神経内科一般 専門医など
|
診療実績
令和5年度 入院患者の疾患別症例数
| 総計 |
401例 |
| 脳梗塞 | 191例 |
| 一過性脳虚血発作 | 8例 |
| 脳出血 | 24例 |
| てんかん | 34例 |
| 中枢神経系感染症 | 20例 |
| 前庭疾患 | 30例 |
| 変性疾患等脳・脊髄・神経・筋疾患 | 52例 |
| 肺炎など内科疾患 | 42例 |
令和4年度 入院患者の疾患別症例数
| 総計 |
365例 |
| 脳梗塞 | 186例 |
| 一過性脳虚血発作 | 11例 |
| 脳出血 | 23例 |
| てんかん | 33例 |
| 中枢神経系感染症 | 15例 |
| 前庭疾患 | 24例 |
| 変性疾患等脳・脊髄・神経・筋疾患 | 46例 |
| 肺炎など内科疾患 | 27例 |
令和3年度 入院患者の疾患別症例数
| 総計 |
404例 |
| 脳梗塞 | 156例 |
| 一過性脳虚血発作 | 12例 |
| てんかん | 51例 |
| 前庭疾患 | 40例 |
| 脳・脊髄疾患 | 20例 |
| その他 | 125例 |