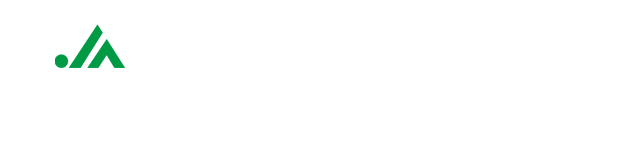指定認定等
地域医療支援病院制度の趣旨・整備計画
- 日常生活圏において必要な医療を確保し、医療機関の機能分化と連携を図る観点から、二次医療圏を単位として医療機関相互の適切な機能分担を図り、その機能連携を進めることが必要とされています。
- 医療は患者の身近な地域で提供されることが望ましいとの観点から、かかりつけ医を地域における第一線の医療機関として位置付け、かかりつけ医を支援するとともに、他の医療機関との適切な役割分担と連携を図っていくことにより地域医療の充実を図る病院を「地域医療支援病院」と位置付け、知事がその名称使用を承認するものです。
-
全ての二次医療圏において、かかりつけ医の支援を通じた地域医療の確立を目指すため、以下の機能その他必要な地域の実情を考慮してその整備目標が設定されています。
・かかりつけ医等からの紹介等、病診連携体制
・共同利用の状況
・救急医療体制
・医療従事者に対する生涯教育等、その資質向上を図るための研修体制
主な承認要件
- 他の医療機関から紹介された患者に対する医療の提供(紹介率 80 %以上)を行っていること。
- 病床、高額医療機器等の共同利用を実施していること。
- 救急医療の提供を行っていること。
- 地域の医療従事者の資質の向上のための研修を実施していること。
- 原則200床以上であること。
- 必要な要件を満たした構造設備を有すること。
地域医療支援病院が行うべき業務内容
- 他の病院や診療所からの紹介患者に対する医療の提供
- 病院施設、設備等の共同利用の実施
- 救急医療の提供
- 地域の医療従事者の資質向上を図るための研修の実施
災害拠点病院とは
- 24時間緊急対応し、災害発生時に被災地内の傷病等の受け入れ及び搬出を行うことが可能な体制を有する(傷病者の受け入れ拠点になりうる・ヘリによる傷病者、医療物資等のピストン輪送を行える)
- 消防機関と連携した医療救護班の派遣体制がある
- ヘリコプター搬送の際には、同乗する医師を派遣できうる
災害訓練実施について
当院は、三重県における地域災害拠点病院の指定を受けており、災害発生時には、被災者の救命・救急治療に対して最大限の対応を行う義務を有する。また、そのようなため、毎年1回災害訓練を計画し、実施することとする。
今回は、休日に大災害(地震災害)が発生し、多数の傷病者が当院に搬送されたとの想定で、病院職員に必要な知識、技術の習得および取るべき適切な役割と迅速な行動を身につけるために、院内災害訓練を実施する。
地域がん診療連携拠点病院とは
厚生労働省は、全国どこでも質の高いがん医療を提供することができるよう、医療の均てん化実現に向け、がん診療連携拠点病院を指定しています。
当院は、平成21年(2009年)に「地域がん診療連携拠点病院」として指定をうけました。以降、専門的ながん医療の提供、がん診療の地域連携協力体制の構築、がん患者・家族に対する相談支援及び情報提供等を行っています。
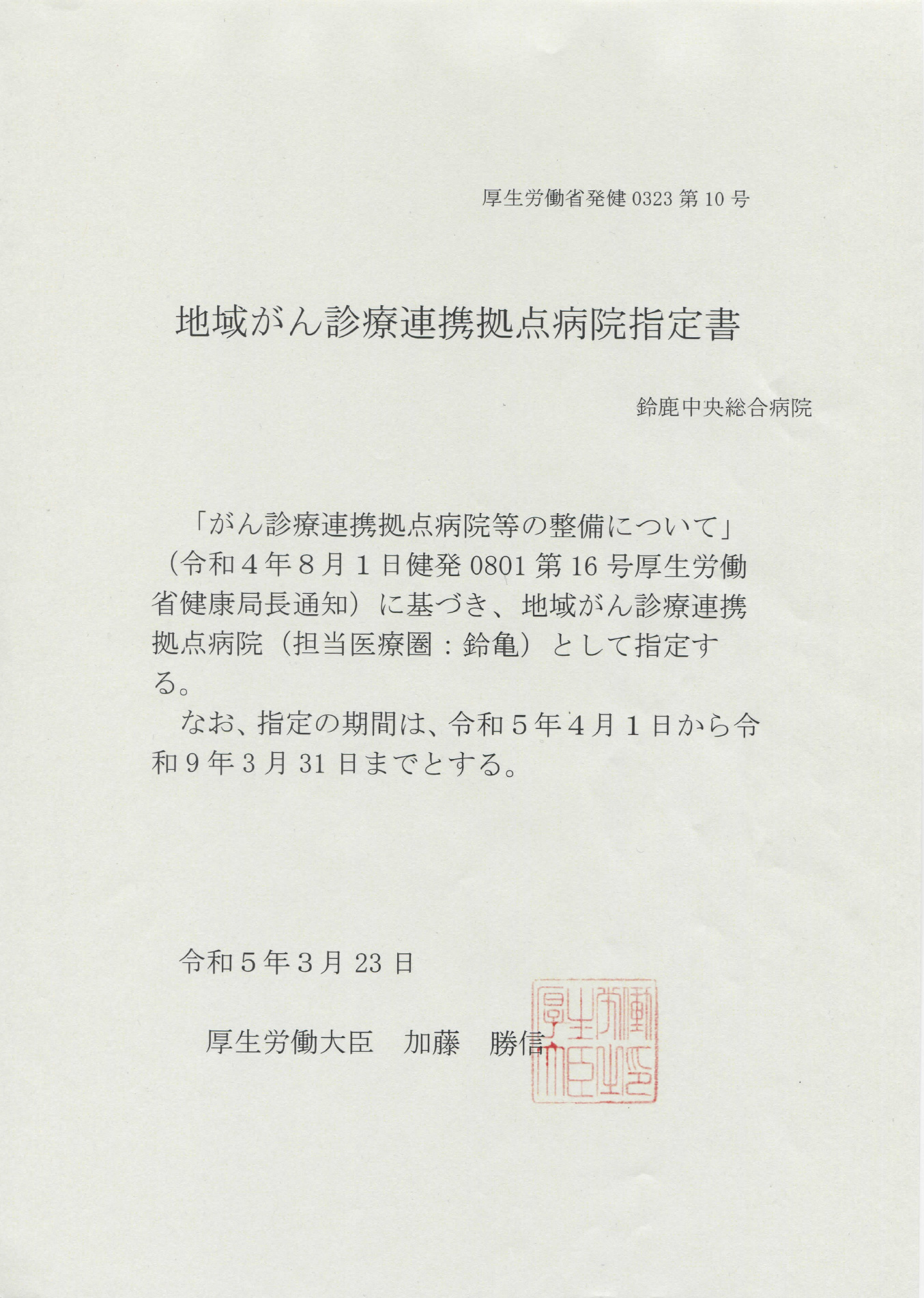
地域がん診療連携拠点病院の役割
- 全人的な質の高いがん医療を提供する体制を確保します
- 「がん相談支援センター」を設け、治療を受けるなかでの気持ち、仕事、経済面、そして介護のことなど療養生活上の不安に対して、がん専門相談員が相談に応じます
- 地域医療機関と綿密な連携を図り、がんの専門的医療の提供をします
- がん診療に従事する医師等に対する研修の機会を提供します
- がん診断における「セカンドオピニオン外来」を設けています
| ●患者・家族のための相談機能 | ||
| ・がん相談支援センターの設置 | 有 | |
| ・公認心理師の配置 | 有 | |
| ・セカンドオピニオンの実施 | 有 | |
| ●診療機能 | ||
| ・化学療法の実施 | 有 | |
| 外来化学療法室の設置 | 有 | 専用病床 20床 |
| ・放射線治療の実施 | 有 | 緩和的照射治療も実施 |
| ・内分泌療法(ホルモン療法の実施) | 有 | |
| ・疼痛緩和の為の神経ブロックの実施 | 無 | 他施設(三重大学医学部附属病院)と連携 |
| ・緩和ケアの実施 | 有 | |
| 緩和ケアチームの整備 | 有 | |
| 緩和ケア外来の実施 | 有 | 第2,4金曜日午後(完全予約制) |
| ・その他がんに関する 専門外来の設置 |
有 | 腫瘍外来(内科)毎週:金曜日午後(要予約) |
| 乳腺外来(外科)毎週:月曜日14:00~(要予約) | ||
▶ 取り扱いがん腫
研修体制
がん診療の連携協力体制として、地域医療圏において院内および地域医療機関の、がん医療に携わる医師、薬剤師、看護師そのほか多くの医療関係者を対象に研修(緩和ケア研修会など)を実施しています。
がん患者さんに対する情報提供
がん診療の連携協力体制として、地域医療圏において院内および地域医療機関の、がん医療に携わる医師、薬剤師、看護師そのほか多くの医療関係者を対象に研修(緩和ケア研修会など)を実施しています。
| ●がん市民公開講座 |
            |
PDCAサイクルについて
PDCAサイクルとは、、Plan(計画) → Do(実行) → Check(評価) → Act(改善)の 4段階を繰り返すことによって、がん診療の質・安全等の改善に取り組んでいます。
臨床研修指定病院とは
当院は 2004 年4月から始まる、新臨床研修制度の管理型臨床研修病院の指定を平成7年4月に厚生労働省から受けました。
注1)管理型臨床研修指定病院とは当院が主体となり研修を実施します。
研修は2年間で、必要な科目は内科、外科、産婦人科、救急、地域医療、小児科、精神科です。
当院に入院病床のない精神科は鈴鹿厚生病院で研修を行います。
注2)研修医は指導医のもと診療します。単独で診療することはありません。
臨床研修とは、医学部を卒業したのちに行われる初期研修をいいます。
医師としての基本的な知識・手技などはこの期間に習得されるため、 医師の教育において特に重要であります。
1968 年以来、「卒後2年以上の臨床研修を行うこと」が努力目標として掲げられ、大多数は大学付属病院で研修をうけておりました。研修医の処遇の問題、診療が高度専門化する一方、プライマリケアに必要な疾患を診療する機会が少ないといった問題等が見直され、新しい臨床研修制度が2004 年 4 月より導入されました。
その基本理念は、「医師としての人格を涵養し、将来の専門性にかかわらず、医学・医療の果たすべき社会的役割を認識しつつ、一般的な診療において頻繁に遭遇する負傷又は疾病に適切に対応できるよう、基本的な診療能力(態度、技能、知識) を身につける。」です。
臨床研修病院の指定をうけるためには、以下の点を中心に厚生労働省の審査を受けます。
すなわち急性期の病院としての機能をはたしていることが指定の条件となります。
1) 研修医が充分に研修できるための一定数以上の指導医、外来患者数、入院患者数、救急患者数、手術件数。
2) 患者の病歴に関する情報を適切に管理していること。
3) 研修に必要な施設、図書、病歴管理の体制が整っている。
4) 研修プログラムが完備されていること。
卒後臨床研修評価機構
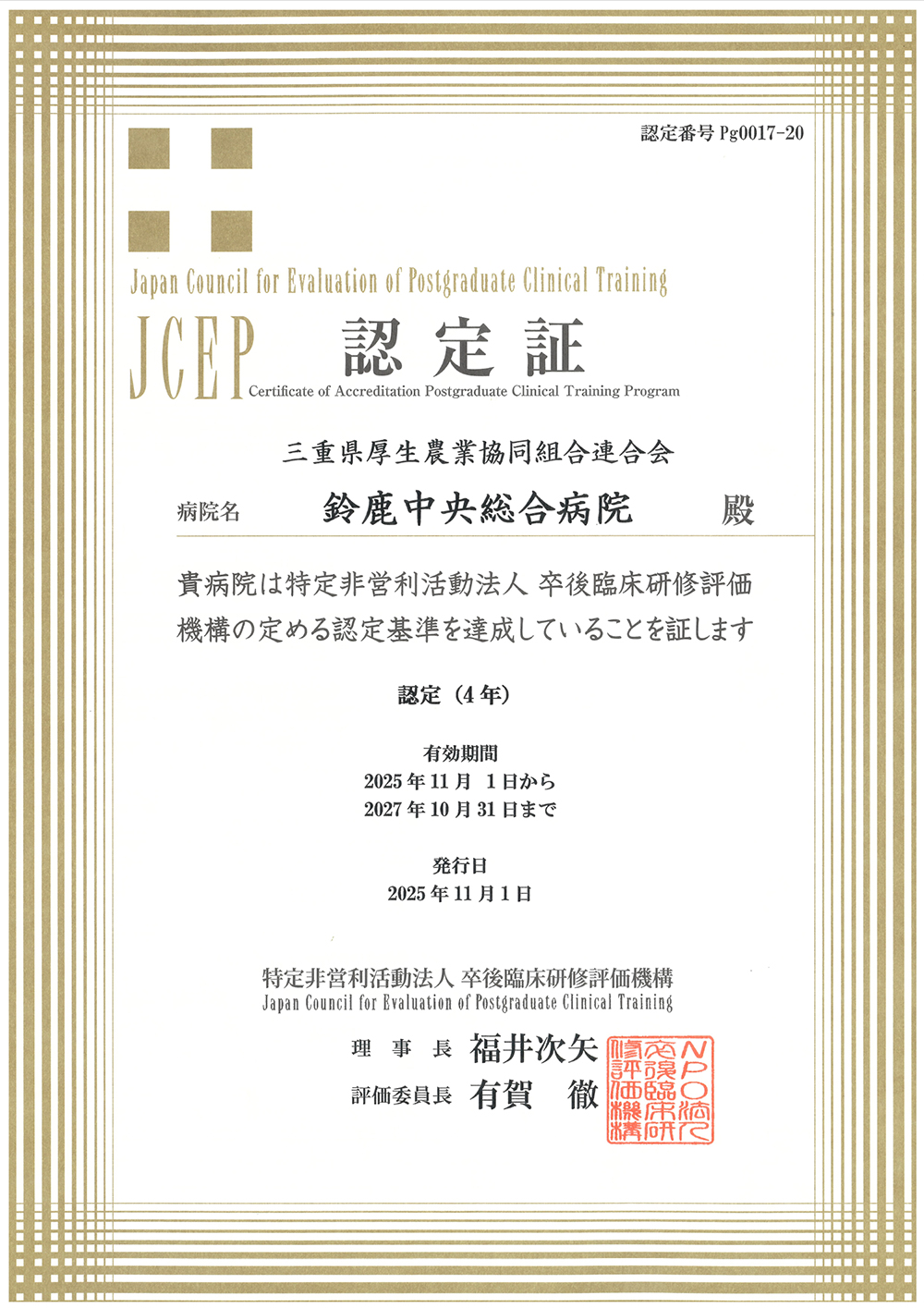
日本医療機能評価認定病院とは
当院は、平成29年10月13日付で病院機能評価の認定(3rdG:Ver1.1)を受けました。平成9年に初回認定を受け、今回で5回目の認定となります。
病院機能評価は、病院において組織全体の運営管理および提供される医療について、第三者機関である財団法人日本医療機能評価機構が中立的な立場で評価されるものです。
全職員一丸となり、苦労しながら準備を進め、一つの目標に邁進し、目標に到達し得た事が何よりの喜びであり、患者さんの視点に立った医療の流れ、それに関わるケアプロセスについて、評価、認定されたことは、日頃の職員の取り組みが評価されたと自負しております。
今後も、当院の理念・基本方針に基づき、安全・安心で質の高い医療の提供に努めてまいります。